2025年07月
AI技術者インタビュー「AI領域へのキャリア転向」
他分野からAI領域に飛び込んだ若手開発者たちの軌跡
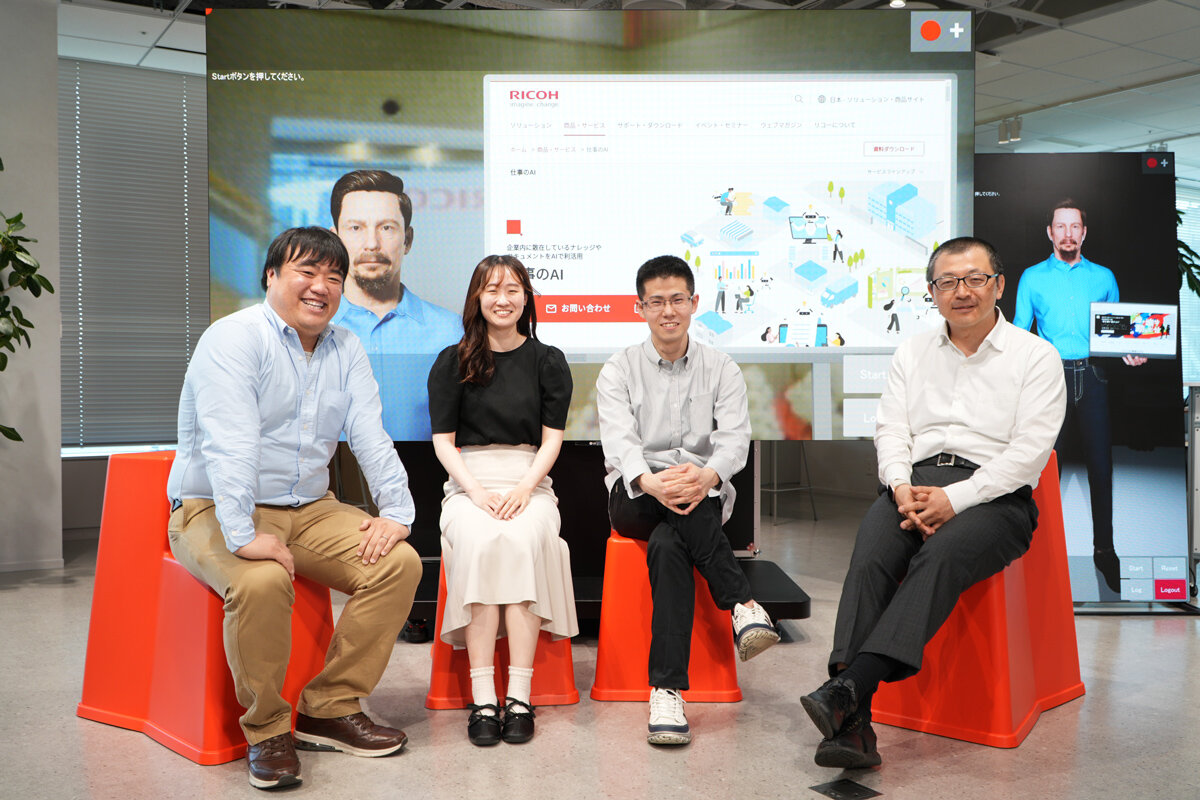
"体験と対話"から生まれたお客様のアイデアや未来構想の具現化を支援するRICOH BUSINESS INNOVATION LOUNGE TOKYO(以下、RICOH BIL TOKYO)。来場者の方からいただくご相談の中でも特に多いのが、いかに生成AIを活用していくべきかということです。
リコーでは様々なAIソリューションの開発に取り組んでおります。そしてリコーのAI技術者らは、長年AI領域に携わってきたメンバーだけではなく他分野から転向してきたメンバーも多く在籍しています。
今回は、実際にAI領域に転向してきた若手開発者らと、リコーデジタルサービスBU AIサービス事業本部 デジタル技術開発センター(Digital Technology development Center:以下、DTC)にて所長を務める鈴木剛が、座談会を実施。
彼らはなぜAI領域へと転向したのか、そしてどのようにAI技術者へと成長していったのか、今後の展望まで語り合いました。
有機半導体、コウモリ、物性物理。もともとAIとは違う領域の研究をしていた3人の若手開発者たち
鈴木:本日は、若手の技術者に話を聞こうということで、企画しました。特にみなさんは、もともとAIに携わってきた方々ではなく、他の領域からAIの分野に入ってきた方々ですよね。
リコー自体もそうですし、日本全体を見ても、分野を超えてAI領域に入っていく人というのはこれから増えていくでしょう。そうした方々にも参考になるお話を本日は伺えればと思っています。そこで、まずはみなさんのキャリア遍歴を教えて下さい。
村沢:私がリコーに入社したのは2013年ですので、現在は入社13年目になります。もともと大学では高分子化学を専攻しており、その中でも有機半導体、いわゆる電気が流れるプラスチックの基礎物性の研究を行っていました。
大学卒業後リコーに入社したのですが、はじめはトナーなどのサプライ製品の設計開発や量産ラインの設計、また品質安定化のための技術開発など一通り経験してきました。
その際に、当時はインダストリー4.0という考え方が流行っていたこともあって、量産工場にAIを導入しよう活動に参画したことがAIに触れるキッカケとなりました。
その活動の中で、機械学習を使った品質安定化に取り組むことでAIの面白さに目覚め、社内公募で当時量産工場向けのAI開発を専門にやっていた部署に異動。そこで画像系のAIに携わるようになっていきました。
その後、2021年にDTCに異動し、データ開発や振動見える化といったプロジェクトを担当。そして2024年より本格的にLLM(大規模言語モデル)に携わるようになり、それからは開発ではなく、お客様との対話を通して案件を進めていくプロジェクトマネジャーのような立場を任されるようになり、現在に至ります。

リコーデジタルサービスBU AIサービス事業本部 AIインテグレーション統括センター DXシステム開発室 システム開発グループ 村沢義寛 (Difyエバンジェリスト)
大学では高分子有機半導体の基礎物性の研究を行う。リコー入社後はEP向けサプライの設計開発・量産工程設計に携わり、量産工場にAIを導入するプロジェクトに参画。機械学習を使った品質安定化に取り組んでいく中でAIの面白さに目覚める。異動後に画像系AI、データ開発などのプロジェクトに関わり、2024年より本格的に生成AIの導入支援・案件PMなどを行う。
源田:私は2024年入社で、今年は2年目になります。学生時代はコウモリの研究をしていました。当時はつなぎを着て、ヘルメットをかぶって洞窟に入り、コウモリを捕まえて、研究室に持ち帰って研究をするといったことをしていました。
コウモリは超音波を発してエコロケーションで周囲の環境を認識するわけですが、そうした音を記録したり、カメラでトラッキングを行ったりして、得られたデータからコウモリが環境に対してどういった行動を取るのか、どういった意思決定を行うのかをAI学習を取り入れてモデル化するという研究を行っていました。
そして大学卒業後、リコーに入社するのですが、キッカケは学生時代に研究を指導してくださっていた方の影響でした。その方はリコーの社員でDTCに在籍されていた方だったので、お話を伺う中で面白そうだなと興味が湧き、リコーに入社することを決めました。
そして入社後はLLM開発領域で、実際に案件をいただき、データをつくって学習させ、モデル調整して評価するという一連の流れを経験してきました。
佐藤:私は大学では博士課程まで進み、物性物理を研究していました。そして物性物理の中でも変分原理を使った計算、それは多数のパラメータを置いてその物性の状態を再現するような計算だったのですが、多数のパラメータ配置が当時流行りだしていたCNN(Convolutional neural network)と合致していて、自身の手法にもCNNを取り入れるようになりました。
長らく物性物理の研究をする中で、そうした研究はゆくゆくは世の中の役に立つとは思っていましたが、博士課程を終えた後は企業に就職し、より直接的に役に立つような研究をしたいと思うようになりました。
そして、就職というのは分野転向する良い機会だと思い、リコーが人工知能を研究開発しているらしいと聞いて興味を持ち、リコーに入社しました。
もちろん、新しい分野であるためはじめは苦労することもありました。たとえば大学での研究でも数値計算をやっていましたが、プログラミング言語がFortranという非常にシンプルなものであったため、オブジェクト指向プログラミングに慣れるまでは苦労しました。
ただ、リコーではコアモジュールを開発しており、そのニューラルネットワークを訓練する際に、多くの人が訓練しやすいインターフェースを被せたパッケージをつくって、全社的に展開しようという試みがあったんですね。
そのプロジェクトに私もアサインされ、まわりへと普及させる活動を行いつつ、自分自身も学習していくことで成長していくことができました。その後LLMが流行り始め、私自身もLLM開発のプロジェクトに参画する運びとなりました。

リコーデジタルサービスBU AIサービス事業本部 デジタル技術開発センター LMM開発室 LMM技術開発グループ 佐藤諒
博士課程では物性物理学の研究を行う。より直接的に役立つ研究をしたいと思いリコーに入社。ニューラルネットワーク訓練をパッケージ化するプロジェクトにアサインされた経験から苦労していたオブジェクト指向プログラミングを習得。その経験を活かしLLM開発プロジェクトに携わるようになり、現在はLMM(Large Multimodal Model:大規模マルチモーダルモデル)&LLM開発をメインに行っている。
鈴木:村沢さんは、工場にAIを導入しようということがキッカケとのことですが、具体的にどのようにAIに触るようになっていきましたか?
村沢:はじめは、AIというよりも、統計的なデータ解析に近い領域、いわゆる品質工学の分野から入っていったのがキッカケではありました。
そして、工場制御のような文脈で、機械学習の手法のひとつである勾配ブースティング決定木の理論などに触れるようになったことで、どんどんとAI分野に入っていったという形でした。
鈴木:源田さんもコウモリの研究からいまではAI分野と、異色の分野転向だとは思うのですが、なぜAIの道に進もうと思ったのですか?
源田:学生時代、研究テーマを決める際に “強化学習” というワードがありまして、そのときはそれがAIだということすら知らなかったんですね。ただ難しそうなテーマだと感じ、どうせ研究するなら難しいことにチャレンジしてみたいと思ったことがキッカケでした。
また、生物は好きなのですが、生物学は苦手で(笑)。そうしてAI領域に触れていくうちに、「最先端のAIを理解できるようになりたい」というのが私自身にとって大きなモチベーションとなり、いままさにAI技術者としてAIに携われることが本当にありがたいと感じています。
まだ入社2年目なので、とりあえず手を動かす、何でもやるという気持ちで取り組んでいるのですが、1年目のときと比べいまでは少しずつできることが増えていて、AI技術者としての成長を実感できています。そうした成長もやりがいに繋がっています。

リコーデジタルサービスBU AIサービス事業本部 デジタル技術開発センター LMM開発室 LMM技術開発グループ 源田祥子
入社2年目。学生時代の専門では、AI学習を取り入れてコウモリのナビゲーションをモデル化するという研究を行う。研究を指導してくれた先輩の影響でリコーに入社。現在はLLM開発領域の一連の流れに携わる。
リコーでは大小様々な案件があるため、他分野からの転向であってもAI技術者としてステップアップできる
鈴木:仕事として新しい分野に突き進むというのは、体系的に知識を身につける必要もあるかと思いますが、みなさんはどのようにして知識や技術を習得していきましたか?
村沢:当然、自ら机に向かって学ぶといった時間は必要だと思います。YouTube含め、いまは学ぶためのコンテンツやツールが充実しているため、基礎的な知識習得はそうしたものを活用しながら学習を進めていきました。
ただ、最も大事なことは実際に仕事としてその分野の現場に飛び込むこと。ただ勉強するだけでなく、実際に手を動かさなければ身につかないですし、やりながら覚えたというのが私自身の実体験でした。
源田:私も同じく、業務としてとにかく手を動かすしかない状況で、当然ながら納期もありますから、何をすればどうなるのかというのを本当に一つずつ覚えていきながら進めていきました。
特に現在の業務では自由と責任のバランスがとても良いと感じています。やりたい事をやれる環境がありつつも、自由だけじゃダメで責任があるからこそ成長できると思っています。
佐藤:クラスの使い方だとか関数の使い方だとか、Pythonになるとたとえばリストなどの標準機能に関わる取り扱いが十分に整備されていたりしますが、それらの選択肢が多岐に渡るため、はじめは扱いに慣れませんでした。
いまではLLMがプログラミングを自分たちの代わりに書くような時代になりましたが、私は実地で練習する機会を与えてもらった経験から、まずは自分でざっと見て大まかに把握するということを繰り返していったことで、AIに対してもスピーディーかつ的確な司令を渡すということができるようになったと感じています。
また、リコーのAI分野に来ている人たちの動向を見ていると、リコーの開発状況は個々の成長実現にもうまく機能しているなと感じています。たとえば、単にファインチューニングして、得た知恵のデータだけ学習させてリリースするといった案件もあれば、アーキテクチャから手を加えていくような難度の高い案件まで、リコーは幅広くやっています。
それはすなわち、ちょうどよくステップアップできる案件があるということで、たとえ他分野からの転向でも立派なAI技術者になれる環境があるというのを、私自身感じました。
鈴木:村沢さんは社内公募で異動されていますが、技術者視点でリコーのそうした社内公募制度についてはどのようにお考えですか?
村沢:長いことリクルーターとしても動いてきまして、これまでも学生や他社の友人からいろいろな話を聞いてきましたが、リコーでは社内公募がしっかりと運用されているなと感じています。
企業に就職して20年、30年と働く中では、どうしても仕事に飽きることもあると思っています。そうしたときに社内公募というキャリアのルートがあると、やる気を損なわずにモチベーション高く働き続けることができますので、それは技術者にとっても非常にメリットとなる制度だと考えています。
鈴木:村沢さんはもともと開発畑出身でありながら、現在はお客様とコミュニケーションを取るようなポジションとなり、見える景色というのもまた大きく変化したのではないかと思います。
村沢:開発畑にいると、お客様の反応やそもそもその技術が誰かの役に立つものなのかどうか、実感を得づらいと感じることもありました。現在はお客様に近い立場で、ダイレクトにお客様の反応をいただけるポジションで働くことができています。
そのため、リコーが開発する生成AIをお客様にお見せして実際に使っていただくことで、「すごい」といったポジティブな反応をいただけたときは、自分たちの技術が役に立てているのだと感じられ、非常にやりがいを感じる瞬間です。
またAI分野というのは非常に変化が激しく、市場には新しいサービスが次から次へと出てきています。そうした中でお客様とお話ししていると「こんなサービスがあるんだけど」などと、お客様の方から新しい情報を持ってきていただけることもあります。そうした新たな気づきが得られることも、面白さのひとつです。

リコーデジタルサービスBU AIサービス事業本部 デジタル技術開発センター 所長 鈴木剛
1999年リコー入社。画像機器向け画像処理アルゴリズム開発、ビッグデータ解析などを経てLLM開発に携わる。
鈴木:特にRICOH BIL TOKYOは、現場担当者の方はもちろん、経営層の方々も来場されるため、様々な視点を持たれている方が多くいらっしゃいます。そうした視点が違うがゆえに、必要としている技術やサービスも違っていて、勉強になることも多いですよね。
RICOH BIL TOKYOのようなファシリティがあるということに対して、みなさんはどのようにお考えですか?
村沢:AIに限らず、実際のモノを見ながら話すというのは非常に大切だと思っています。会議室でただパソコンの画面を見せながらお話をするのではなく、RICOH BIL TOKYOのような場所で実物のデモを見せながらお話したほうが、お客様もイメージしやすいですし、私たちからしても説明がしやすい。ぜひ多くの方に来場いただきたいです。
佐藤:従来であれば展示会などでしか披露できなかったのが、RICOH BIL TOKYOでは常時、来場者に合わせて開発したものをお見せすることができます。開発の状況を公開しやすくなっているというのは、技術者にとっても大きなメリットです。
そして、来場される皆様は何かしらの課題を抱えているわけですが、課題を認識できていないケースも多々あり得るわけです。そうしたときに、RICOH BIL TOKYOでリコーの多様なAIソリューションに触れること自体が、来場者自身の課題を掘り出す作業になるだろうと思うと、双方にメリットがある空間だと思っています。
源田:ワクワクできるかどうかは、とても大切なことだと私は思っています。やはり画面越しではなく、対面でお会いして、さらにAIを目で見える形にした実機があるからこそ、来場されるトップマネジメント層の方々にもワクワクいただける仕組みがRICOH BIL TOKYOにはあると感じています。
「面白そう」を大切にする文化があるからこそ、AI技術者が興味あることに挑戦し、活躍できる環境がリコーにはある
鈴木:自身の経験をふまえて、これからAIに取り組む人に伝えたいこと、またリコーでAI技術者として働く魅力はどういったところにあると感じているのか、教えて下さい。
源田:いまはAIというのは誰もが注目する分野で、AIに取り組みたいと思えば取り組むことができるような環境だと思っています。そのため、AIに興味があるのであれば、あとは一歩踏み出すだけ。AIを学ぶ環境もありますし、AI技術者の需要もあるわけですから、まずは飛び込んでみてほしいなと思っています。
そして私自身、一歩を踏み出し、いまリコーでAI技術者として働いていますが、リコーは良い意味で想像を裏切る会社でした。学生のときに想像していた社会人像とはまったく違って、リコーでの日々というのは毎日が本当に楽しく、ポジティブな印象を抱くことばかり。本当に働きやすい環境だと感じています。
村沢:AI開発というのは、まったく知らない人からすると、すごく難しくて高尚なことをやっているイメージがあると思うのですが、AIというのはあくまでもツールであって、AIをどのように使いこなすかを考えることが大切だと考えています。
そのため、 “AIを開発する” というよりも、 “何かをするためにAIを活用する” といった捉え方をしたほうがいいだろうと思っています。
そしてリコーという会社は、トップダウンではなく、ボトムアップで「これをやったら面白そう」といった好奇心から各個人が取り組み始めるといった空気感があると感じています。そうした雰囲気はAI分野と相性が良いと思っていて、AI分野に合った仕事の進め方ができるというのが、リコーの魅力だと感じています。
佐藤:AIというのは本当にいま広く普及していて、自然言語処理をするというだけには留まらなくなっています。そうしたときに、いかにAIの応用先を見つけるかというスキルが問われると思っています。
たとえば言葉であれば言葉のルールがあり、音楽であれば音楽理論があって、数学なら数式があるなど、その領域の秩序が何かしらあるわけです。つまり、AIを使ってどういった問題解決をしたいのか、それはどういった秩序を持った問題なのかというのを客観的に見ることが大切。そうした本質を捉えることで、AIの応用できる幅というのは無限大に広がるのだと思っています。
そう考えたときに、先ほど村沢さんからもありましたが、自身の興味や関心をぶつけやすい環境がリコーにはあり、AI技術者としては成果を上げやすい環境だと思っています。そして社歴などにとらわれず、誰もが正当に評価されるため、自由度高く、挑戦心を持って働きたい人には向いている環境だと感じています。
AI同士が競争し合い、進化する未来。リコーのAIをより多くの人に認知してもらうために
鈴木:今回は座談会ということで、私からだけでなく、お互いに聞きたいことを聞く質問コーナーを設けてみました。まずは源田さんからお二人に「将来の夢や目標は?」とありますが、村沢さん、佐藤さんはいかがでしょう?
村沢:いま達成したいことは、リコーのAIの認知度をもっと高めたいということでしょうか。私はお客様とお話しする機会が多いですが、お客様からは「リコーはこんなAIやっていたんだ」と驚かれることは珍しくなく、まだまだ認知度が低いなと日々感じています。
お客様からもAI関連のトピックをお話しいただけるとより良いコミュニケーションがはかれると思いますので、そうした機会を増やすべく、リコーのAIをより広く認知してもらえるような活動を行っていければと思っています。
佐藤:AIサービス事業本部 の梅津本部長の指揮のもとで動いている、バーチャルヒューマンのプロジェクトが非常に面白いと感じており、同じように自律的に動けるAIの搭載先を展開したいというのが目標としてあります。
たとえば中国であれば資本力もあるがゆえに、ロボットにAIを搭載するというケースはあると思うのですが、ロボットでなくともバーチャル上で体が動くAIをつくり、お客様自身もバーチャル上でAIとやり取りしていくことはもちろん、AI同士がその環境から学習し、競争していく場があるべきだろうと。
飛躍した話のようにも思われるかもしれませんが、人類も何万年前まではホモ・サピエンスだけでなく、他人類がちゃんと存在していて、その中で競争があったわけです。その競争を勝ち抜き、他人類が絶滅して、我々という人類種はいまここまで進化を遂げた。同様に、AIも競争して勝ち抜く場がバーチャル空間上でもいいのであれば、人的リソースをかけて開発する以上にスピードで進化していくでしょうし、そうしたAI開発を自動化していきたいというのが目標としてあります。
鈴木:それこそAIの黎明期には、「AIの課題は身体性にある」といったことも議論されていました。身体性というのは、外界とインタラクションする実態、すなわちインターフェースが重要だろうと。
そうした話が、またいま俎上に上がるというのは、ようやくこの時代になってそうした取り組みができるようになったからこそだなと感じました。
では最後に、村沢さんから源田さん、佐藤さんへの質問です。「みなさんバックボーンが様々ですが、ずばりAIをやっていて楽しいですか?」ということですが、いかがですか?

源田:何かできることが増えたり、達成できたときは楽しいと思えますが、まだまだ本当にわからないことだらけで苦しいときもあります。どちらかと言えば、いまはまだ「楽しい」と思えるようになれるよう、努力しているというのが正直なところです。
佐藤:LLMとビジョンエンコーダーを繋ぎ、訓練をするということを以前に取り組んだのですが、はじめは見たものに対して反応がなかったんですね。しかし、訓練を工夫すると見たものを認識できる瞬間がって、そのときは知能の神秘を感じ、非常に面白いなと感じました。
普段はコードとのにらめっこで、いかに眠気に勝つかが大変ではありますが(笑)。
鈴木:今回、長年AI領域にいたわけではない、他の分野からAIに飛び込んできたみなさんのお話を聞いてきましたが、実際に自らつくったものが動いたときの喜びであったり、顧客接点での感じることというのは、実はAIに限らず、どの分野でも共通した部分だろうというのをあらためて感じました。
さらに、AIをツールとして活用し、自分の興味あること、フォーカスしたいことにフォーカスできるということが、いまのAI時代の特徴だということも、あらためて思いました。
我々のAIサービス事業本部というのは、事業開発を担う部門やインテグレーションを担う部門、さらにRICOH BIL TOKYOとった様々な機能が揃っており、その上集まっているメンバーも多様なバックグラウンド、そして様々な興味関心を持った人たちばかり。
こうした状況というのは非常にダイナミックで、いろいろと面白いことがこれからも出てくるだろうと期待しています。今回はみなさん、本当にありがとうございました。
■取材後記
それぞれ異なる専門分野から転向しAI技術者として活躍されている若手の皆さんが、口を揃えて「AIはツール、AIを使って何をするのか」とお話されていたことがとても印象的でした。
新しい分野、しかも世界的に興味関心の高い分野で、スピード感を持って様々なアイデアを実現しているリコーのAIサービス開発の秘密が垣間見える座談会に、編集者としてもとてもワクワクした体験となりました。




