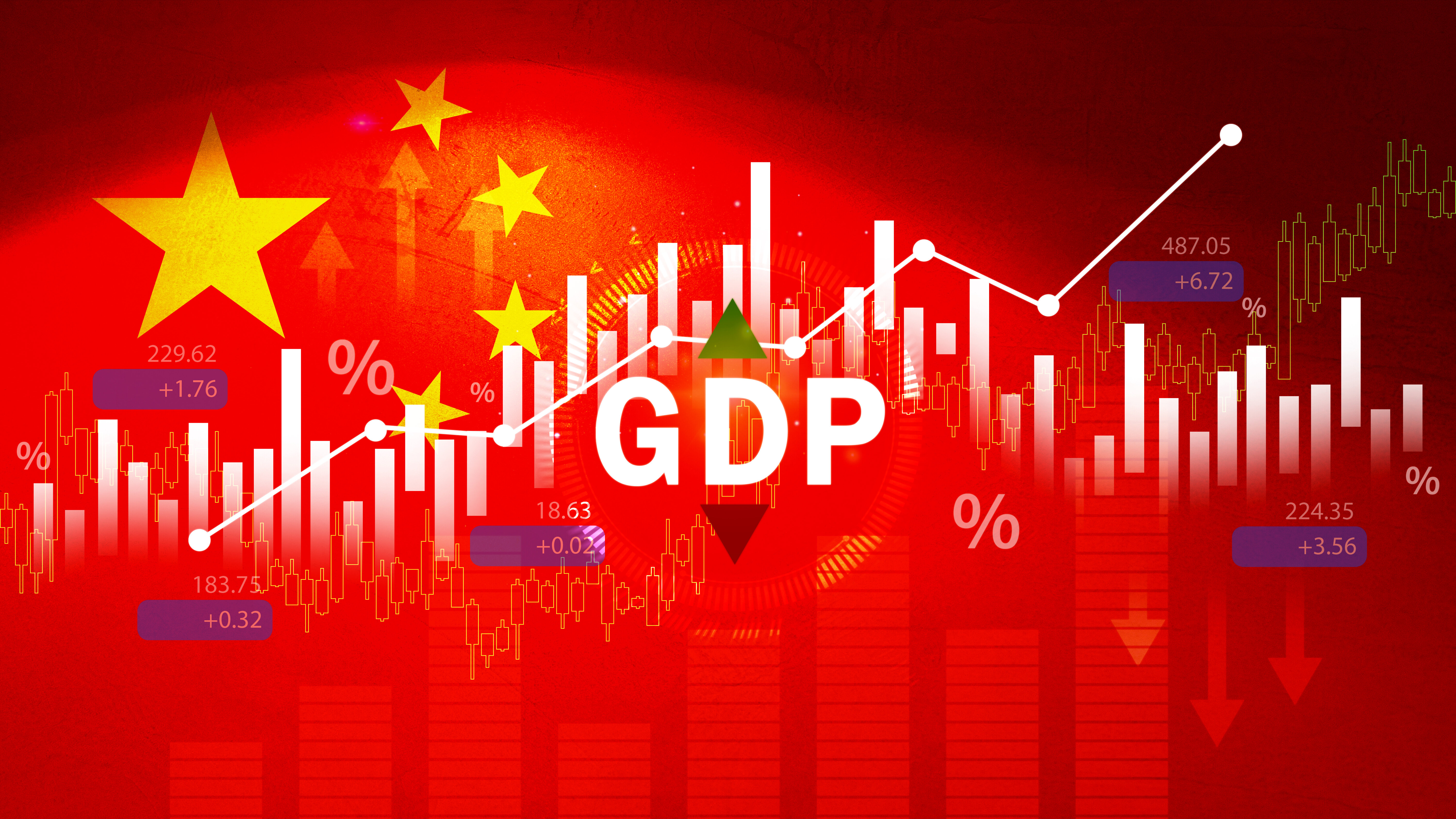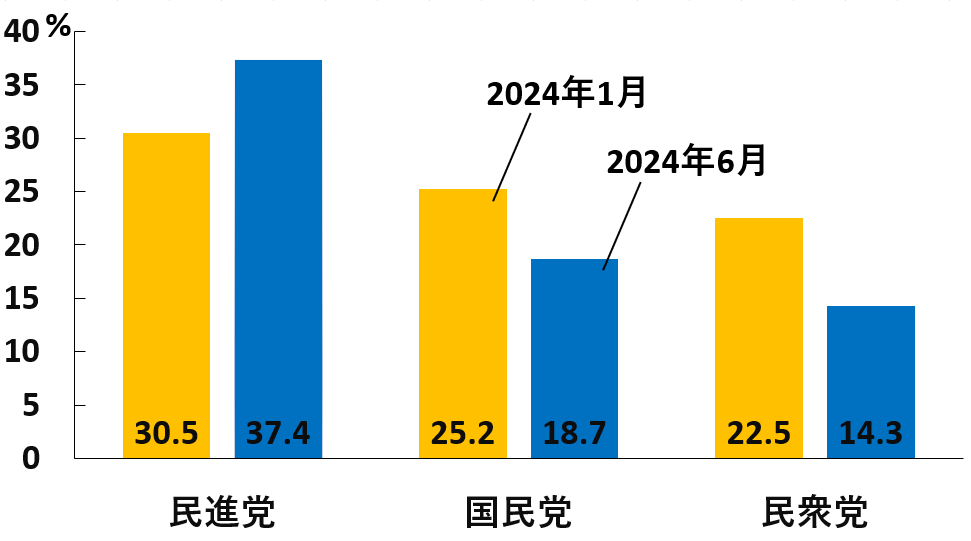なぜ、タイとカンボジアが軍事衝突
《この記事で分かること》
Q タイとカンボジアが今年5月に軍事衝突した。その背景は?
A 19世紀のフランス植民地下で曖昧だった国境地域の領有権をめぐる対立が背景にある。1962年に国際司法裁判所は国境地帯にある寺院をカンボジア領と判断したが、周辺地域の帰属をめぐって対立が続いた。
Q 両国の国内政治も影響しているのか。
A タイでは衝突後に政権が交代。カンボジアでは政権世襲への不満をそらす狙いも衝突の背景にあったとされる。
Q 今後も緊張が続くのか。
A 10月のASEAN首脳会議で和平合意に署名したが、タイ政府は11月に履行を一時停止。それでも、両国の経済・人的交流の結びつきは強く、観光・労働・インフラ整備などの分野で共存の動きが広がっている。
タイ、カンボジア両国が互いに領有権を主張する国境地域で5月に軍事衝突し、数十人が死傷、戦闘機による空爆という事態に発展した。東南アジア諸国連合(ASEAN)構成国で隣り合う両国の緊張は今も続いている。日系企業が数多く進出している両国の関係は安定するのか。文化・歴史的な背景を概観した上で、経済や人的交流を通じた両国関係の今後を探ってみたい。(共著 編集長 舟橋良治)
「アンコール文明」の栄華
タイとカンボジアはかつて、アユタヤ王朝とクメール帝国という強力な王権を中心とする統治体制をそれぞれ築き、1000年以上の時をかけて複雑な関係を構築してきた。

アンコールワット
クメール帝国は現在のカンボジアを中心にアンコール文明を花開かせ、高度な水利システムや壮麗な宗教建築を発展させた。アンコールワット、バイヨン、タ・プロームといった遺跡群は単なる観光資源ではなく、国家的アイデンティティーの中核としてカンボジア国民にとって今も精神的支柱である。一方、タイ側ではアユタヤ王朝が14世紀から勢力を拡大、交易と軍事に長(た)けた政権として知られた。
そうした中、15世紀にアユタヤ軍がアンコールを占領。大規模な運河、堤防、貯水池など水利インフラの維持が困難になったほか、干ばつや季節風による被害などが重なり、クメール帝国が崩壊した。カンボジアにとっては栄華の記憶として、タイにとっては地域の盟主となり独自文化を形成した物語の舞台としてアンコール文明が共有されることとなった。この歴史が現在の両国関係やナショナリズムに深く影響しているのは否定できない。
尾を引く植民地時代
19世紀後半になると、欧州列強の植民地政策が両国の運命を分かつ。フランスがインドシナ半島に進出し、カンボジアを保護国化した。タイ(当時シャム王国)は独立を維持したが、その過程で領土の一部を割譲せざるを得なかった。とりわけ1893年の仏泰(タイ)戦争の後、1904年と07年に結んだフランスとシャム王国が結んだ条約によって現在の国境線が画定された。しかし、カンボジア領となった国境地域にあるプレアビヒア寺院を含む一帯の帰属をシャム王国がその後も主張。今も残る火種となった。
1962年、国際司法裁判所はプレアビヒア寺院をカンボジア領とする判断を下した。しかし、その周辺領域に関しては明確な線引きがされず、現在に至るまで曖昧なままである。2008年から11年にかけて両軍による断続的な衝突が起こり、死傷者と避難民を出した。これにより、歴史と文化遺産、そしてナショナリズムが織りなす複雑な国境問題が過去の遺物ではなく、現在進行形の安全保障問題であることが改めて示された。
首相が失脚する事態に
今年5月、タイとカンボジアの国境地帯において再び軍事的緊張が高まり、両国の軍が交戦するという事態が発生した。数十人の死傷者が出たほか、一部地域で空爆が行われた。この軍事衝突や国境問題をめぐる対応が引き金となってタイで政権が交代し、不安定な政治情勢を浮き彫りにした。
 (出所)adobe stock=AIによる生成
(出所)adobe stock=AIによる生成
その経緯を振り返ってみたい。軍事衝突で緊張が高まっていた6月、タイのペートンタン・シナワット首相(当時、タクシン元首相の娘)が、家族ぐるみで親交のあったカンボジアのフン・セン前首相と秘密に電話会談した際、同氏を「おじさん」と呼んで友好的だった一方、タイ軍の幹部を「自分の敵」と批判。その音声が6月になってカンボジア側から流出すると、タイ国民の愛国心を刺激した。
そして国軍の影響下にある憲法裁判所は国家倫理違反にあたると判断し、ペートンタン氏は失職。野党だった保守系「タイ誇り党」のアヌティン・チャーンウィーラクーン党首が9月、新首相に選出された。政権交代は、タイにおける国軍の影響力を再認識させた。
「世襲」への国民の不満
カンボジアでは、フン・セン長期政権から息子のフン・マネット首相への移行が進行していた。統治の継続性維持と世代交代を模索していたが、「世襲」への国民の不満が高まっていたとも言われる。この不満を抑えるため、タイという外部との衝突を利用、国内統治の手段としているとの分析もされている。
両国における政権交代や権力移行には、ナショナリズムが複雑な影を投げかけている。国内の不満や分断が高まる局面では、外部との緊張が政治的に利用される傾向が強まる。今回の衝突も、その文脈において理解されるべきであろう。
和平合意に署名
タイとカンボジアの両首脳は、10月下旬にマレーシアで開かれた東南アジア諸国連合(ASEAN)関連首脳会議の場で、トランプ米大統領の立ち会いの下、和平合意に署名した。しかし、国境検問所は5月の軍事衝突時から閉鎖されたままだった。アヌティン首相の「タイ誇り党」は国境地帯の保守層が支持基盤で、こうした保守系支持者への配慮が必要なためとされる。
そうした中、タイ政府は11月10日、自軍兵士が係争地で地雷を踏んで負傷した事態を受けて和平合意の履行を停止すると発表した。その後、銃撃戦が起きて死傷者が出たとされ、対立が再び激化する懸念も出ている。
それでも、両国はASEANの構成国として経済的に密接な関係を有している。タイはカンボジアの主要な貿易相手国であり、工業製品、食品加工、小売り、金融、観光といった多様な分野で大きな存在感を持つ。カンボジアは、若年労働力と繊維・農業の基盤を有し、タイ経済の裾野を支えている。タイ国内で就労するカンボジア人は多く、あらゆる分野で不可欠な役割を担っている。
「二つの国、一つの目的地」
カンボジアのフン・マネット政権はインフラ連結や観光連携を通じた関係修復を目指し、タイのアヌティン首相も平和的な解決を最優先課題に掲げている。
両国政府は就労の枠組みや人身取引の防止策を強化。賃金未払いや労働災害、煩雑な在留手続きといった現場の課題に対処するための制度整備も進め、経済関係は年々、深化していた。
近年は国境経済特区(SEZ)を整備し、①国境をまたぐ道路・鉄道網の再構築②物流インフラのデジタル化―などを推進。また、港湾の相互接続を通じて両国の経済関係を強化してきた。サプライチェーンの安定化と投資環境の改善も期待され、国境地域には自動車部品メーカーなど日系企業も多数進出している。
観光面では「二つの国、一つの目的地」構想が再始動し、アンコール遺跡とバンコク旧市街、プーケットやシアヌークビルを結ぶ観光ルートが人気を集めている。滞在日数や観光消費の増加が見込まれる。

バンコクで最も人気のある、エメラルド仏がまつられた寺院
「ワット・プラ・シー・ラッタナーサーサダーラーム(ワット・プラケーオ)」
「現場発」の共存
近年は政府間のみならず、民間レベルの協力や地域社会の連携も進みつつある。例えば、国境地帯の市場や国をまたぐ「観光回廊」の整備を通じて、地元住民が経済利益を直接得る仕組みが育ち始めている。こうした「現場発」の共存は対立を和らげる役割が期待できるだろう。
さらに、SNSやユーチューブを通じたクロスボーダー消費が拡大。音楽・映画・ゲームといったポップカルチャーを通じた相互理解が進展している。とりわけ若年層の間では、国境を越えたコラボレーションが進んでおり、ナショナリズムや固定観念を緩和する役割を演じている。
争いではなく共生の象徴へ
タイとカンボジアは、歴史的・文化的遺産や現代的課題が複雑に絡み合いながら微妙な「均衡」を保ってきた。そうした中で起きた国境地域での衝突は、両国の政治に複雑な波紋を広げ、タイでは政党や軍、王室、司法が統治に複雑に関与、政権が交代する事態に至った。カンボジアでは世襲の形で政権の世代交代が進行。若年層の将来不安、社会的不平等、経済格差、ナショナリズムといった問題が、外交や国境政策に影響する可能性もある。
両国の関係は、今後も曲折が予想される。それでも対立を乗り越えて、国境管理や経済協力の枠組みを再構築・強化する取り組みが始まっている。さまざまな制度整備に加え、市民の対話促進などを通じた多層的な信頼構築の努力が今後ますます重要となろう。
関係の安定には歴史を乗り越え、人材交流や交通インフラ構築などを通じて連携・協力を推進するしかない。互いに領有権を主張して軍事衝突の火種となったプレアビヒア寺院の遺跡が争いではなく、未来に向けた希望と共生の象徴に変わっていくことを願いたい。

プレアビヒアの遺跡
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!