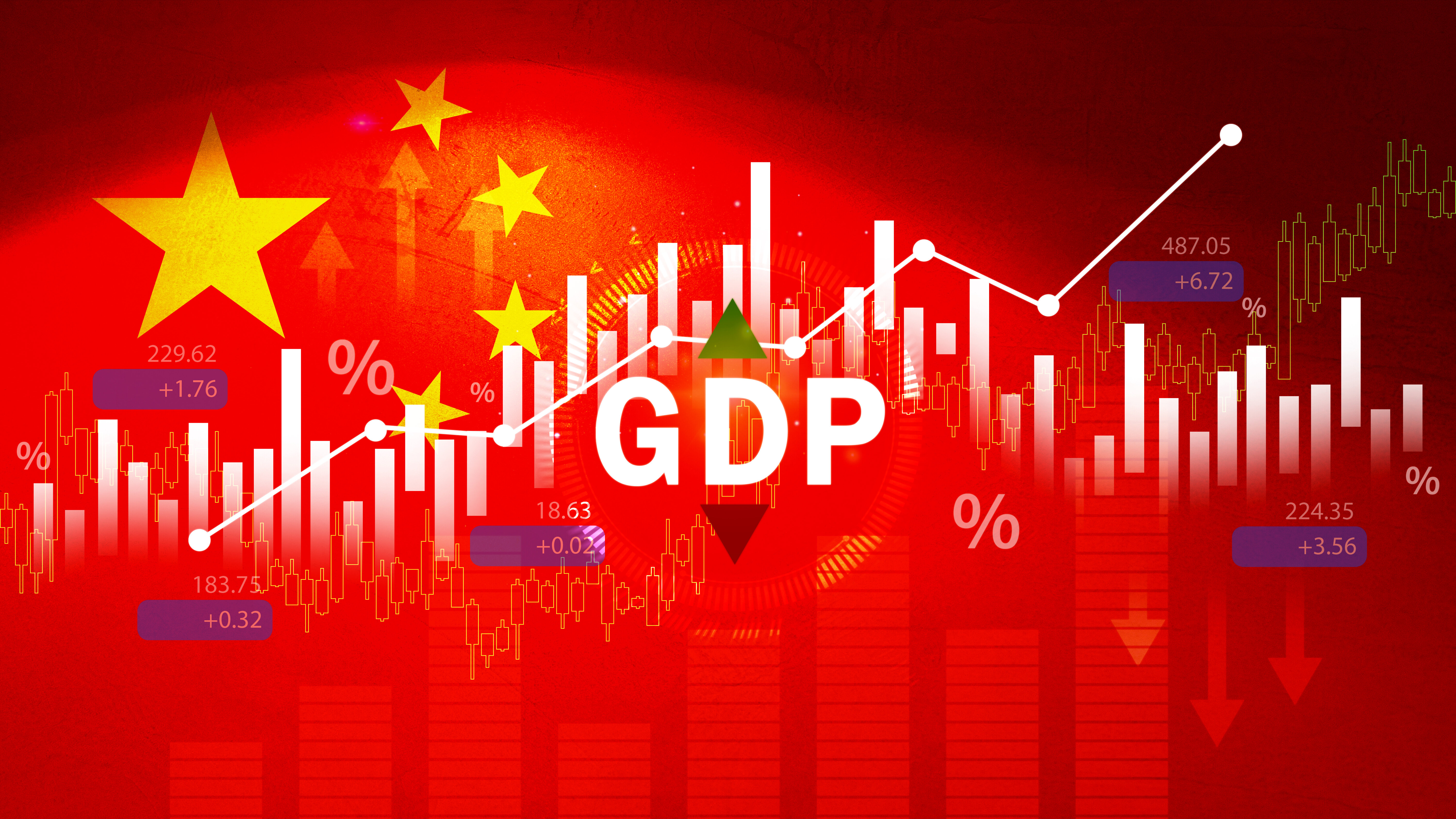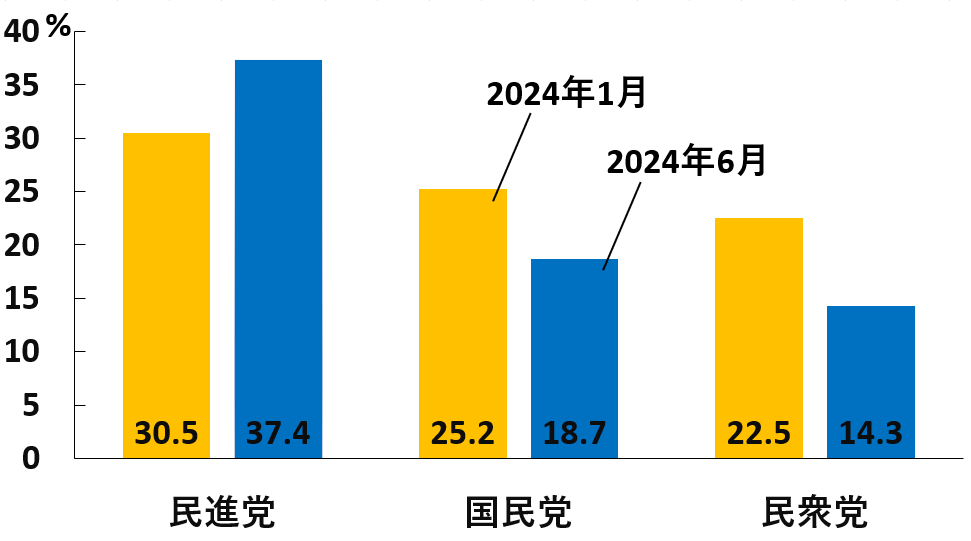フライドチキンが大好き! 中国の外食事情
「配給制」→「市場化」が食を多様化
ラーメン、チャーハン、ギョーザ、シューマイ...。世界無形文化遺産の「和食」を誇る日本人も、中国から来た食を楽しんでいる。というより、中華料理のない食生活は考えられない。ところで、彼の国ではどんな食を楽しんでいるのだろうか?
中国の食を考える上で、キーワードとなるのが「市場化」である。中国共産党は昨年11月の「三中全会」で、「市場機能の拡大」を政策課題の中心に掲げた。従来方針の「消費力の拡大」や「サービス産業の発展」とあわせ、外食産業は追い風を受けている。
日米中入り乱れ、街にあふれる外食チェーン
今、中国の都市を歩くと、至る所で外食チェーン店の看板が目立つ。ケンタッキー・フライドチキン(KFC)、マクドナルド、スターバックス、ピザハット...。日本からも、吉野家やCoco壱番屋、サイゼリヤなどが進出。地元中国系も負けていない。火鍋料理の小肥羊(シャオフェイヤン)やカジュアル中華の真功夫(ヂェンコンフ)などが、庶民の人気を集めている。

中でもKFCの躍進は凄まじく、中国全土に約4000店を構え、ライバルであるマクドナルドの約1700店を大きく引き離す。KFCの世界3万7000店のうち、1割強が中国に集中している。
KFCの強さの秘訣は、メニューの徹底した現地化にある。北京ダック風のチキンや四川風味の牛肉炒めを小麦生地で巻いたもの、中華風スープ、白飯に肉団子などをのせたメニューも用意されており、「従業員食堂」の趣がある。
外食チェーンには、まだ開拓の余地がありそうだ。人口10万人当たりのKFCの店舗数は、日本では0.93店に達するが、中国はまだ0.30店。マクドナルドに至っては、日本の2.60店に対して0.13店と、20分の1にすぎない。
外食比率の高い上海人 日本料理が大人気
中国で「市場化」が最も進んだ最大都市、上海の外食事情を紹介しよう。中心オフィス街の某大手企業の場合、現地従業員の外食比率は朝も昼も8割に達するという。
朝はパン、茹でトウモロコシ、蒸し饅頭をコンビニで買う人もいるが、中国生まれのファストフードというべき油餅(ヨウビン)や煎餅(ジエンビン)をほお張る人もいる。いずれも小麦粉の生地を鉄板で焼いたものだが、皮の厚さや具材が違う。上海人はこうした朝食を思い思いの場所で食べる。停留所でバスを待ちながら、歩道を歩きながら、あるいはオフィスに着いてからでも...
一方、ランチ事情はどうか。先ほどの大手企業に聞くと、弁当持参が20%、レストラン45%、従業員食堂30%、コンビニなどの弁当が5%といったところだそうだ。
上海のレストラン事情は、グルメサイト「大衆点評網」で概観できる。料理別に見ると、中華系では上海料理が7338店でトップ。以下、四川3706店、広東1907店、湖南1481店と続く。外国料理では、日本2272店、韓国947店、イタリア料理258店となっている(2013年12月10日現在)。
全体では、日本料理店が上海と四川に次いで堂々の第三位。さらに、利用客の書き込みに基づく「トップ10レストラン」のうち、5つを日本料理が占める。日本人が中華を楽しむように、彼らも和食を楽しんでいるのだ。最近の健康志向に合致するほか、キメ細やかな調理法が人気の秘訣のようだ。外国料理が上位に食い込むぐらい、中国の外食市場は成熟してきた。
かつては「配給制度」が食を担う
こうした外食の市場化は当たり前に思われるかもしれない。しかし中国の場合、全くの異次元から出発していることを忘れてはならない。かつては、社会主義を蝕むものとして外食を含む市場を排除する社会だったからだ。
1970年代まで、中国は名実ともに配給の社会だった。職場は「単位」と称される個人の所属場所であると同時に、住居から食堂、学校、保育所、理髪所、劇場に至るまで生活の全てを丸抱えする場だった。食糧や布などの必需品は「配給切符制度」に基づいて地方政府が提供したが、その一方で賃金は低く抑えられた。つまり、モノやサービスの供給のほとんどが、市場を介していなかった。当然、外食産業が育まれる余地もない。
1970年代末から、ようやく中国は改革開放の路線に転換した。とはいえ、すぐに市場社会が誕生したわけではない。1989年の天安門事件を機に、一時は資本主義や市場化を警戒する保守勢力が息を吹き返すこともあった。
それを押しのけたのが、鄧小平である。1992年、中国南方への巡回で保守派を批判し、改革促進の檄を飛ばした。翌年、「社会主義市場経済」への移行を公式に宣言し、配給切符制度を撤廃した。
それから間もない1994年春、筆者は初めて中国大陸の土を踏んだ。当時、北京市内の外交官向けマンションが集中するエリアでさえ、外食チェーンはピザハットだけ。夜になると、物乞いや花売りの子供たちがこの店の灯りに群がるほど、周りに飲食店が少なかった。
それから20年後、この界隈は飲食店が密集しており、隔世の感がある。統計と重ねてみると、現在の中国の宿泊・飲食業の総生産額は、1994年の1009億元(約1.7兆円)から、2012年には1兆464億元(約17.7兆円)と10倍以上に拡大している。
市場が育む「食」のクオリティー
改革開放以前の市場なき時代には、中国の伝統的な食文化はむしろ台湾や香港で継承され、発展していた。台湾各地の夜市でひしめき合う無数の外食店は、食が市場に育まれることを証明している。
例えば、小龍包の発祥は上海だが、台湾の人気レストラン「鼎泰豊」(ディンタイフォン)の評価がすこぶる高い。1980年代に訪れた時、台北の創業店では芳しい蒸気が通りを歩く人々を誘っていた。1993年には米紙ニューヨーク・タイムズによって「世界十大レストラン」の一つに選ばれている。
もちろん、大陸中国の食も今や市場化の中で質を高めている。北京ダックの世界では、周恩来元首相が愛用したレストラン「全聚徳」(チュアンジュダ)が圧倒的に有名だったが、最近の北京では新興の専門店「大董」(ダードン)が大人気。そのクオリティーの高さには目を見張る。「大衆点評網」の評価でも老舗を大きく上回っている。
習近平体制が「市場化」を加速させる中で、中国の食文化はいっそう豊かさを増していくだろう。それは日本人の食生活とも無縁ではない。既に東京・渋谷のセンター街には、中国発の外食チェーンが上陸を果たしている。
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!