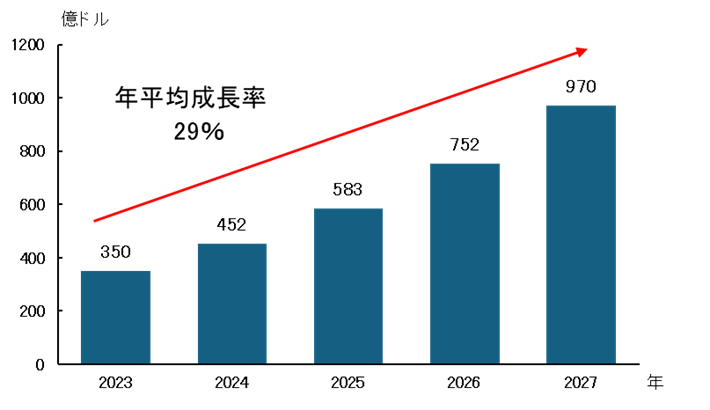AIが変える社会とリスクへの備えを
急速に進化・普及しつつあるAI(人工知能)は産業構造や形態、雇用・労働に大きな影響を及ぼそうとしている。AIはどこまで進歩し、働き方はどのように変わるのか。AI活用が広がった社会が抱えるリスクは何か。AIの研究開発、実用化に詳しい大阪大学先導的学際研究機構の栄藤稔教授(元NTTドコモ執行役員・イノベーション統括部長)にAIの可能性とリスク、活用時に注力するべきポイントについて聞いた。

劇的に増える人の意思決定
――AIに人はどのように関わることになるのか
現状の生成AIでも、プログラムを書き、ソフトウエアを作成できるようになっている。プログラムを書く人は確実に不要になる。既にサイトの立ち上げ程度なら生成AIを活用すると2~3時間で可能だ。(スタッフが)20~30人の優れたソフト開発会社は、AIでプログラムを自動的に作成することよって生産性を大きく向上させている。間もなくソフトがソフトを作成できる時代になるだろう。
一方、AIが出力した結果を検証したり、判断したりする高度な仕事だけが残る。数日かかっていたような企画書作成やリサーチがすぐにできるようになり、人が確認し、実施する意思決定は劇的に増え、負荷が高まる。私は(ハイレベルなWeb検索エージェントの)DeepSearchなどAIをフル活用しているが、仕事の密度が高まり、朝から仕事をして午前11時ごろには「脳がへとへと」になっている。
人材育成、制度の壁
――高度な判断もAIがこなし、労働が不要になる可能性は?
例えば弁護士事務所やコンサルタント会社で補助的な仕事は、ほぼ不要になる。補助的な仕事がなくなることで、高度な人材をどのように育成するのか、問題になることが予測できる。高度な判断をする弁護士やコンサルタント自身も不要になる恐れは技術的にはある。
ただし制度の壁がある。弁護士や医師は法律で人であることが規定されている。AIと人の境界を規定する組織・制度などを変えない限り、この部分は今のところ残るだろう。
人と同じように予測
――AIが人間の知能を超える「シンギュラリティ」はすぐにでもやってくる?
シンギュラリティや汎用(はんよう)AIの定義の問題はあるが、「AIによるAIの生成、進化」ができるようになり、社会を大変革させるということであれば、2030年までにやってくるだろう。
実は、人間の脳もAIも基本原理は単純であり、素子数(細胞数)も追いついてきている。「意識を持つ・持たない」は分からないが、特定の画像などを見て次に何が起きるのか、人と同じような予測は可能になっている。
開発コスト、劇的に下がる
――AIとロボットなどが結びつくフィジカルAIも実用化は間近なのか
既にロボットの動きをサイバー空間でAIが学習できるようになっている。視覚情報をリアルタイムでロボットの関節の動きに反映できるようになれば、かなりリアルなシミュレーションが可能になる。サイバー空間でのシミュレーションによってロボットの開発コストは劇的に下がる。ただ、リアルタイムでの触覚の取り込みはもう少し時間がかかる。
こうした取り組みで最も進んでいる地域が、中国・杭州だ。新興AI企業ディープシーク(深度求索)やユニツリー・ロボティクス(宇樹科技)といった最先端のAI、ロボット開発の企業が集まっている。彼らはあくまで実利に基づいた研究開発をしている。中国はロボットもAIも自己技術でほぼ開発可能になっている。開発コストも安く農業や介護などで利用するサービスロボットならば、300万円程度。米国製の3分の1から2分の1以下だ。日本は数千万円する精密で高価な産業用ロボの開発はできるが、農業やサービスで使うロボットに高精密は不要だ。
ソフトウエア・ファーストに転換を
――日本がすべきことは
ソフトウエアを最上位に据えて製品やサービス全体を規定するソフトウエア・ファーストという意識が大手機械メーカーになく、ハード中心に考えていることがAI時代には大きな弱点になる。ソフトウエア・ファーストの世界では、製品やサービスを提供しながら徐々に完成形にもっていく。国内の大手メーカーは、ハード思考であり、初めから完璧な製品・サービスを提供しようとする。そうすると開発競争に遅れてしまう。
国全体で見ると中国には人材と製造業があり、米国には巨大プラットフォームがある。両国には軍民共用(デュアルユース)の政策支援もある。日本は精密機械産業が段々と弱まっている上、高等教育に大きな問題を抱えている。AI関連の最先端研究は、ほぼデュアルユースであり対応を改善する必要がある。
セキュリティーに注力を
――高等教育を改善し、ソフトウエア・ファーストになれば日本もAI開発で最先端を走れる?
現実的には中国のロボットを使い、海外のAIを自らの組織向けにカスタマイズして使うしかないだろう。その際に情報を盗まれたり、漏洩(ろうえい)したりすることがないように監視利用技術に注力すべきだ。AIを信頼性高く利用することに力を注ぐことが現実的ではないだろうか。
――AI社会は良いことばかりではない?
セキュリティーが最も心配になる。今はマルウェアといったウイルスではなく、AIがオンライン会議の偽動画を作成、主催して情報を盗んだり、金品をだまし取ったりすることが横行している。外国政府が絡んでいる実例もある。AIが主催するオンライン会議をみても、偽動画であるかどうか、ほぼ区別がつかない。
セキュリティーに対してどのように対応するか?例えば欧州のAI法のようにAI企業に「プログラムソースをオープンにせよ」と規制しても進化が速いのでどれほどの意味があるか、疑問だ。
◇栄藤稔氏略歴
兵庫県出身。1985年広島大学工学修士修了、松下電器産業(現パナソニック)入社。MPEG(画像符号化)の標準化に取り組んだのち、2000年 NTTドコモへ。14年同社執行役員・イノベーション統括部長。15年子会社みらい翻訳社長として機械翻訳事業を立ち上げ。1993年大阪大学博士(工学)取得、2017年 同大学先導的学際研究機構教授に就任。
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!