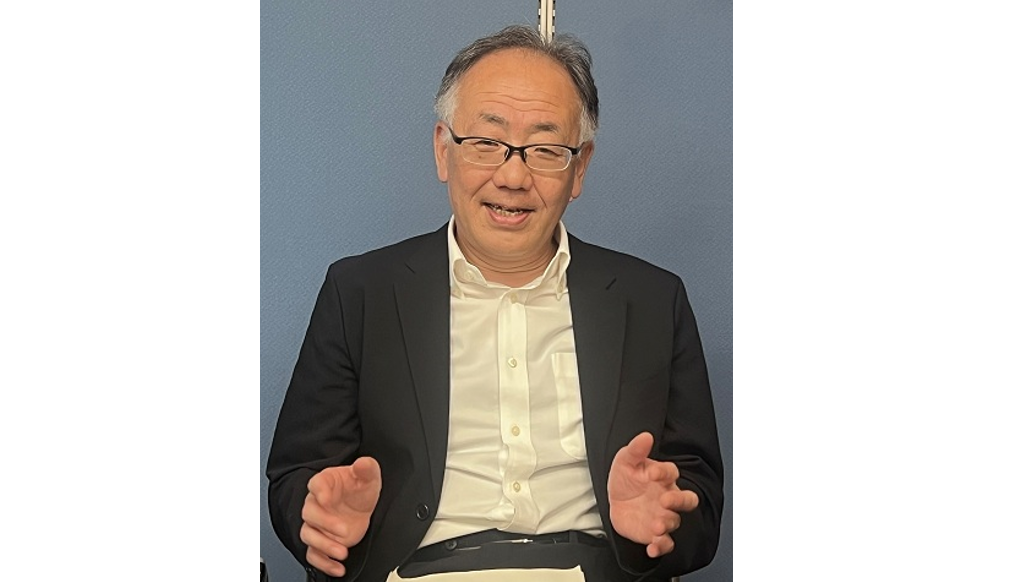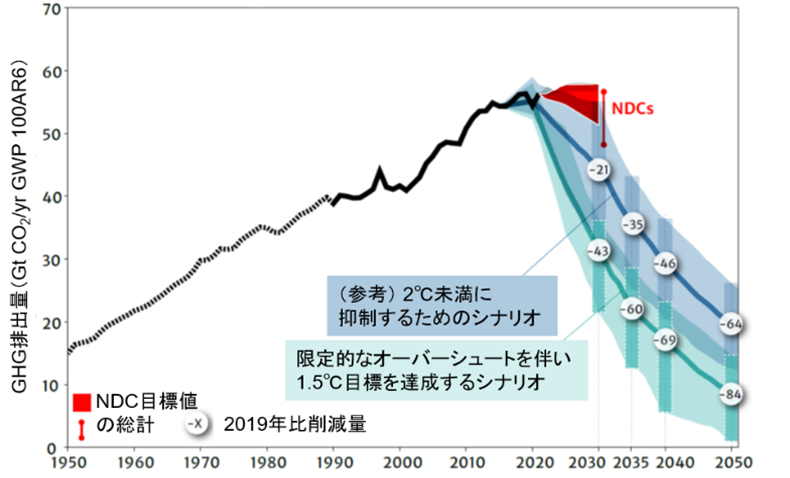「あまちゃん」地元でバイオマス事業
=官民連携で厄介者が新たな価値生む=
2013年に放送されたNHKの連続テレビ小説、「あまちゃん」―。そのロケ地として知られる岩手県久慈市を訪れた。海沿いの道路を車で走ると、高台に白いビニールハウスが並ぶ一角が姿を現す。東京ドームより広い敷地に60棟のハウスを擁する県内最大級のキノコ栽培施設だ。実はこの巨大施設の暖房には、地元の森林資源が活用されている。市内の企業などによって設立され、この再生可能事業を手掛ける久慈バイオマスエネルギー(本社久慈市)を訪ねた。
バイオマスとは生物資源(bio)の量(mass)を表す言葉で、「再生可能な生物由来の有機性資源(ただし、石油や石炭のような化石燃料は除く)」を指す。久慈市では、バイオマスのうち特に木材を活用する「木質バイオマス」事業を進めている。
 キノコ栽培ハウス
キノコ栽培ハウス
 (右) 久慈市林業水産課の係長・熊谷望さん
(右) 久慈市林業水産課の係長・熊谷望さん
(中央)久慈バイオマスエネルギーの代表取締役・日當和孝さん
(左) マルヒ製材の取締役・日當千晶さん
久慈市は朝ドラで描かれた「北限の海女」が活躍する地でありで、昔から海の幸で有名。一方で森林が市の面積の約86%を占め、林業や関連産業の集積地でもある。このため、市は2008年に地元の木材をエネルギーとして活用するバイオマス事業の検討を始めた。
だが、実現までの道のりは平坦ではなかった。2011年3月に東日本大震災が発生すると、計画はいったん保留に。復興事業として瓦礫の木材を燃料として利用する案も浮上したが、久慈市では予想以上に早く処理が進み、これも立ち消えになった。
「それでもバイオマス事業実現への熱意は消えなかった」―。久慈市の林業水産課係長の熊谷望さんは振り返る。市職員らが検討を重ねるうち、ゴミ扱いされ、お金を払って処分していた「バーク」に目が留まった。
 燃料となるバークの保管庫
燃料となるバークの保管庫
製材業では加工時にまず木の皮を剥く。こうして生じる樹皮のくずがバークだ。事業に参加するマルヒ製材専務取締役であり、久慈バイオマスエネルギーの代表も兼ねる日當和孝さんは「使い道がなく、厄介なものとして扱われていた」という。バークを燃やして熱供給ができれば、バイオマス事業と廃棄物の削減の二つを同時に実現できるわけだ。
久慈市が調査したところ、バークを含めた木質燃料を1日40トン程度は確保できることが分かった。大手メーカーがこの量に合わせてプラントの仕様を検討。バークを燃料に加工する上で欠かせない乾燥工程については、専門業者の協力を得て実現の可能性が見えてきた。
設備の概要が固まると、熱の供給先を探さなければならない。当初は地元で木材の乾燥に使ってもらう計画だったが、「熱が余ってしまうことが分かり、再検討が必要になった」(日當さん)―。このとき手を挙げたのが、市内でキノコ栽培に取り組んでいた越戸きのこ園だ。もともと事業を拡大する構想があり、地元の資源を活用する方向性にも賛同して参加を決めた。
こうして2014年2月、主な関係者が出資して久慈バイオマスエネルギーが設立された。久慈市は土地を有償提供し、大手メーカーがプラントの施工と運営サポートを担当。森林組合と林業事業者が燃料となるバークを提供する仕組みも整い、2016年9月にはパイプラインを通じて越戸きのこ園に温風を送る事業がスタートした。ビニールハウスでのシイタケ栽培は順調に軌道に乗り、2017年度には約470トンを出荷できたという。
 キノコ栽培ハウスの中で育つしいたけ
キノコ栽培ハウスの中で育つしいたけ
久慈バイオマスエネルギーが熱供給と並ぶ事業の柱と位置付けるのが、排熱を利用した木質チップの生産だ。水分を含んだ木片を乾燥させることでボイラーの燃料に変え、周辺の施設に提供する。これは、見方によっては熱を木質チップに貯め込んでいるのと同じ。言い換えると、バークを燃やして発生させた熱を、パイプという「オンライン」で供給するだけでなく、遠隔地のボイラーに「オフライン」で送る形になる。
これが久慈バイオマスエネルギーの収益性を高めるブレークスルーとなった。市は公共施設などにチップを使うボイラーの設置を進める。熊谷さんは「事業拡大に対応できるよう、更なる設置場所の調査も進めている」と話す。同事業は、東北再生可能エネルギー利活用大賞(2017年)、第1回エコプロアワード(2018年)で農林水産大臣賞を受賞。市内外から「久慈モデル」への注目が集まっている。
 久慈バイオマスエネルギーのプラント
久慈バイオマスエネルギーのプラント
久慈市の成功は、バークという厄介者を燃料にする技術の開発に加え、自治体や大手メーカー、複数の地元企業による垣根を越えた連携がカギだった。多くの事業者が集まることで、「廃棄物の有効利用」や「化石燃料消費の削減」といった当初目的にとどまらず、周辺に「農産品の安定供給」や「熱のオフライン供給」といった新たな価値が生まれた。こうした官民連携の形は、地域の社会課題を解決するモデルケースになる可能性を秘めているのではないか。
(写真)筆者 PENTAX WG-3
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!