産業革命から学び、備える(下) ~AI時代に求められるビジョン~
蒸気機関と石炭を基盤として18世紀に始まった第1次産業革命、電気と石油の利用を通じた第2次革命は、国内総生産(GDP)上昇や、所得分配、雇用構造などの変革をもたらした。今回の「下」では、コンピューター時代をもたらした第3次産業革命を振り返った上で、同様の経済的インパクトをもたらす可能性が高い、人工知能(AI)時代に求められる経済社会のビジョンについて考えたい。
コンピューターとインターネットの興隆
20世紀後半の第3次産業革命は情報通信技術(ICT)の普及によって知識経済を形成し、サービス産業比率を高めた。コンピューター化は企業の事務処理コストを削減し、国際競争力を強化。経済の在り様を大きく変えた。

コンピューターは1960年代の汎用(はんよう)機から始まり、80年代後半のパーソナルコンピューター、90年代後半のインターネット普及へと進展した。これらは電子商取引やオンライン広告、クラウドサービスなど新たなビジネスモデルを創出し、GDPのサービス部門寄与を高めた。
雇用面では、プログラマーやネットワーク管理者などの高いスキルが求められる職種が増加する一方、単純事務や一部の製造職は自動化によって減少。このスキル偏重型雇用は、賃金格差の拡大や労働市場の二極化をもたらした。
すなわち、中位技能のルーチンタスク(定型化・パターン化した作業)が縮小し、抽象的な分析や創造にかかわる上位技能と、対人サービスなど自動化できない下位技能の領域がそれぞれ伸びているのだ。ICTはまた、設計や開発を本社に残しつつ生産やバックオフィス機能を海外に移転するオフショアリングを容易にした。
デジタル市場では規模の経済とネットワーク効果が「スーパースター企業」を生み、利益と高給が一部企業・一部人材に集中する。その結果、産業全体の労働分配率は低下し、交渉力の低い就業者ほど景気変動の打撃を受けやすくなった。さらに、プラットフォームを仲介する雇用拡大は非正規やギグワーク(雇用契約を結ばず、デジタルプラットフォームなどを介した単発・短時間の働き方)の比重を高め、アルゴリズムによる評価や監督が労働の裁量や仕事の自律性を狭め、長時間労働や報酬の不安定性といった問題を再び顕在化させた。

フードデリバリーで働く女性
テレワークやクラウドソーシング(インターネットを通じた不特定多数への業務委託)の普及は就業機会を広げた反面、デジタルデバイドやスキル・ミスマッチが地域間・世代間の格差として表れた。また、既存の社内昇進や長期訓練に依拠してきた労働の仕組みは、短いサイクルの技術更新、資格の陳腐化に十分に対応できない局面が増えた。
第3次産業革命は、労働者の再訓練と職務再設計、労働移動の円滑化、最低限のセーフティネット整備などをセットで進めない限り、生産性上昇の果実が広く浸透しにくいという課題を「陰画」として浮かび上がらせたと言える。
AI時代の黎明期
現代はAI利用の黎明(れいめい)期。ビジネスモデルや雇用、所得分配など経済社会にどのような影響を与えるか未知数なのが現状だろう。電力や石油利用が本格的に進んだ第2次産業革命になぞらえれば、依然としてポイントソリューション段階にあり、議事録作成や検索など既存業務の一部置き換えが中心である。雇用面では、定型的な文書作成や情報整理、一次的な分析やチェックといったルーチンタスクの比重が高い職務に影響が現れており、同じ名前の職種でも担当するタスクによって影響が異なる。
また、文章の自動要約やプログラミングコードの作成補完などで熟練者が担うタスクの生産性が上がる一方、初心者がエントリー業務を学習する機会が減る。このため、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)などの再設計が求められる。アルゴリズムによる業務割り当てや評価の可視化は労務管理を精緻化するが、AIによる重要業績評価指標(KPI)の最適化により、短期的な目標をこなすことが労働の評価基準となる。これにより、「やらされ感」が増加し、自ら職務を全うしようとする自律性が下がるリスクも抱える。
今後は、AIカメラや自動運転車、AIロボットといったアプリケーションソリューション段階に移行。業務全体の統合・保全、データ運用といった周辺技能が厚みを増し、現場のオペレーションは省人化と一人で多数のタスクをこなす多能工化が同時進行する。
産業構造全体をAI前提で再設計するシステムソリューション段階では、サプライチェーンやサービス提供の設計自体の再編が進み、中位技能のルーチン部門が圧縮される。その一方で経営層に属する戦略立案や組織再編、ステークホルダーとの関係構築などをAIが補完し、職の二極化が現在より強まる可能性が高い。
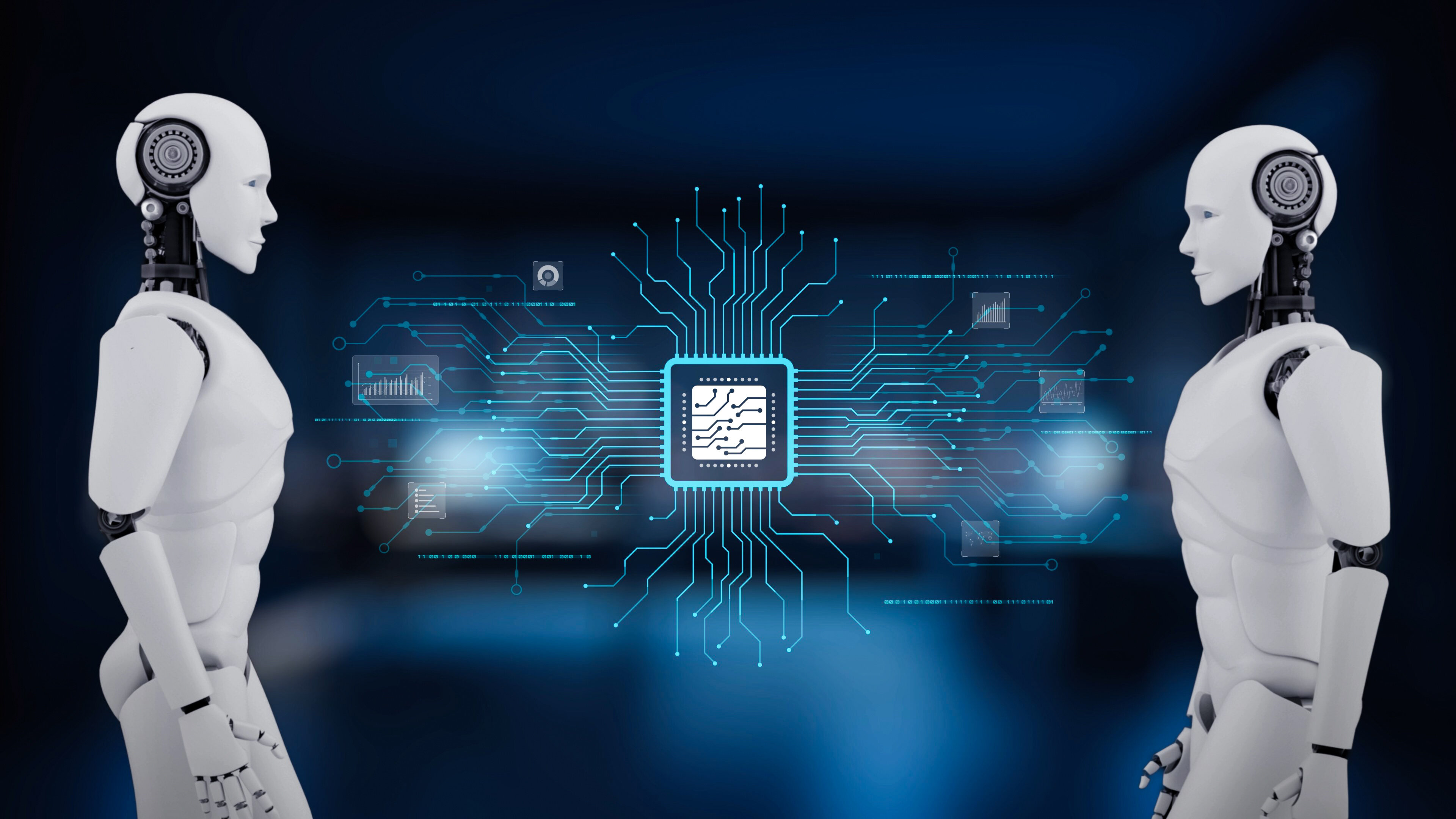
職業構造の再編、避けられず
AIは生産性向上によるGDP押し上げ効果とともに、資本集約型産業の比率を第3次産業革命時より高める可能性がある。これにより、初期投資負担が大企業に集中し、中小企業は参入障壁に直面する恐れがある。
また第3次産業革命が生んだ「スーパースター企業」への利益集中と経営者報酬の高額化が従来より進みやすい。産業全体の労働分配率が一段と低下する懸念があり、「勝者総取り」が地域や企業規模、職種間の賃金格差を拡大させやすい。アウトソーシングやギグワーク型の契約形態など周辺業務における、労働時間管理や安全、衛生、補償といった問題も今後の政策課題となろう。
一方でAI時代は、自動車の普及により産業構造が抜本的に変化し、大衆市場が形成されるといった形の過去の産業革命と同様、職業構造の再構築が避けられない。生成AIサービス、AIを使った医療診断や教育支援など新規市場の形成は、新たな雇用と付加価値創出の契機となる。データエンジニアリングやAIプロダクトマネジメントなど専門職が厚みを増し、これらは高いスキルが不可欠だ。
AI普及で失業するミドル層を含む多くの人々に学習機会を提供できるかが、雇用の流動化と再雇用、社会の安定を左右する。労働移動や再教育(リスキリング)政策、所得再分配の制度設計が経済の安定成長に不可欠だろう。

具体的には、企業は職務をタスク別に分類して「AIに代替されやすい定型」と「AI補完で価値が増す非定型・対人」に再編成し、配置転換を計画的に行う必要がある。それでも、移行期には第1次、第2次の産業革命時と同様に、摩擦的失業や地域間格差が生じやすい。このため、職業訓練や移動支援、職務経歴のポータブル(持ち運び)化や可視化を組み合わせたり、生活費を保証するような保険や職業訓練休暇、学び直し投資への税制優遇などでリスクを緩和したりすることが有効である。
加えて、①アルゴリズムによる評価や賃金査定、解雇判断の透明性と説明責任の明確化②労働者のデータ権(雇用管理上の自身の個人データを編集・削除する権利)保証③ワーキングプアを加速させないように下請けやギグワークの最低賃金基準など生活基盤を保証する制度の導入―といったデジタル時代の労使ルールを整備しなければ、効率化の果実が賃金や雇用安定、学習機会に十分還元されにくい。
求められる新時代の構想
18世紀から20世紀末まで連綿と続いた産業革命の歴史は、新技術が経済成長をけん引する一方で、その恩恵が社会全体に広がるまでには長い年月を要し、雇用や所得分配に大きな影響を与えた。

AIの普及もまた、業務効率化からビジネスモデル再設計へと進化する過程で、GDPや生産性を押し上げるとともに、雇用構造や賃金分布を変容させ得る。企業や個人、政策当局は、これまでの歴史や経験を踏まえ、技術導入の波に合わせた経済・社会制度の再構築に備える必要がある。持続可能な成長と社会の安定を両立させるためには、経済的視点と社会的視点の双方からAI時代の構想を描くことが求められる。
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!
新西 誠人





